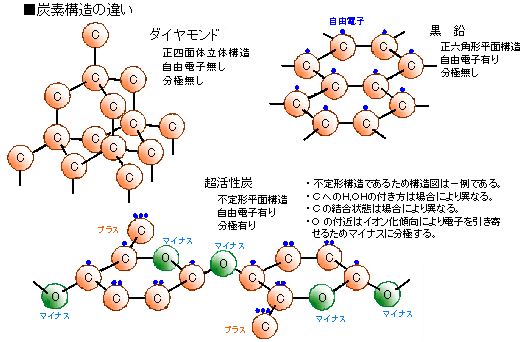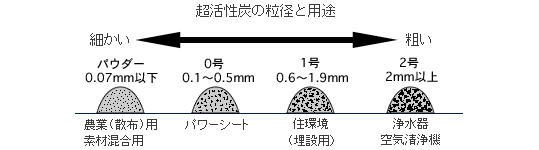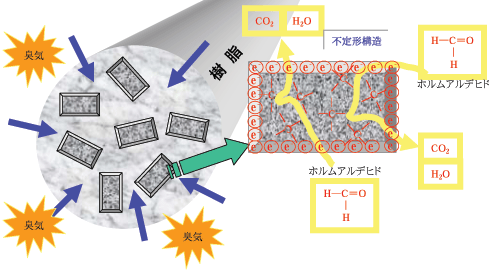超活性炭は真空状態下で、1,100℃以上の温度にて熱処理を加えて生成された活性炭で、炭素化率95%以上、比表面積は1g当たり1,700m2以上で、pHが8.0〜11.0 という特徴を持っています。これは通常の活性炭と比べて、遙かに優れた物理性を持 っています。
製法上の特徴(特許出願中)から通常の活性炭がスポットとして多孔質(非貫通)であるのに対して、超活性炭の細孔は貫通した超微細な細孔(直径5〜10Å)で、理論的な水の最小分子集団(4.4分子で7〜8Å)を楽に通過させる直径であり、水をクラスター化させることができます。
更に説明しますと、物理的には超活性炭は毛細管孔隙の塊であると言えます。また、結晶構造を持っていない不定形構造になっている事と、微量の酸素を骨格内に含有している事により、骨格内部に永久分極性(プラスとマイナスの両極性が分散している状態)を持っていると考えられます。分極による静電引力(クーロン力)によって、様々な物質を引き寄せ、各種の環境悪化原因となっている分子を強力に排除・分解する性質を持っています。
また、大量に発生する特定周波数の輻射波の影響により、一般の水をクラスター化する働きが認められています。水のクラスター化と電磁場域が相乗して、水のポテンシャルパワーを顕在化する働きがあります。
これらの特徴(性質・性能)は、生体内に対しても顕著に働き、血液・体液の循環も 通常より遙かにスムーズに行われると考えられます。
私たちは、炭を用いた農法について、30年以上の成功と失敗を繰り返し、1996年 頃ようやく超活性炭に辿り着きました。農業に限らず、様々な分野での利用価値が認められており、現在研究開発段階の材料です。
注1)水分子集団のクラスター細分化の理論は、植物に対する水吸収効果が向上することから考えられる推論であり、未解明な点が多く、物理学の世界で研究が進められています。
注2)超活性炭の分極性およびその効果については、消臭効果の持続性から考えられる推論であり、未解明な点が多く、物理学の世界で研究が進められています。
|
|